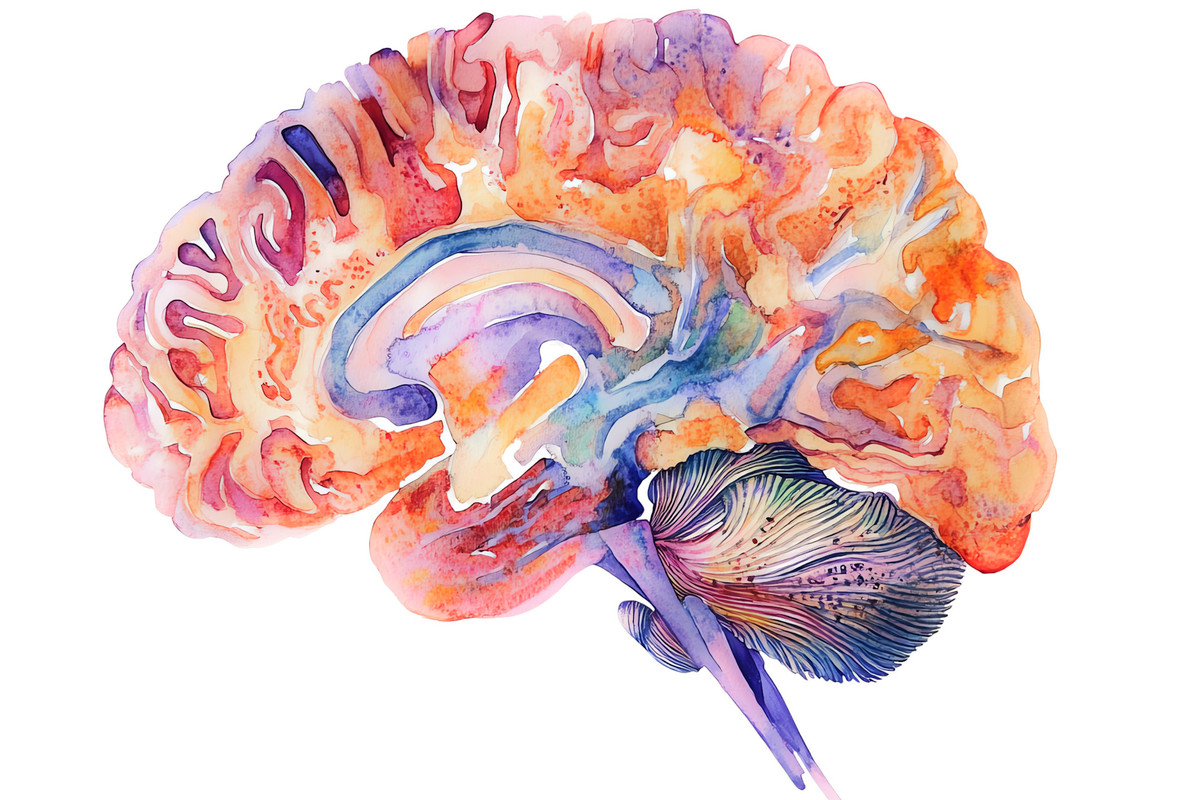
浸透する言葉
2025/11/23
今こうして脳を学ぶことへの
1番のきっかけになったのは
脳を学ぶことは「制御系の知識」ではなく、
生命の表現を読み解くための感性訓練なんです。
という言葉。
それが私の学びたい想いに
スッと浸透してくる様に感じられ
言わば「生命の振る舞い」を
少しでも読み解く事ができれば…
学びたいの源泉には
そんな願いがあるのだと思えたから。
小脳半球、虫部に続き
今回は小脳片葉についても学べた事で
小脳全体へのイメージが先ずは大枠で捉えられ
また、発達過程で小脳の機能が
どんな風に育まれていくのかが
少しずつクリアになっていく様で面白かった。
今どきのお子さん達は
小学校高学年になると塾が忙しくなり
それまで続けてきたバレエやダンスの時間を
プッツリと終わらせてしまうケースも少なくないとよく伺うが、
「学童期から思春期は小脳全体の機能が成熟に向かって仕上がる時期であり、
この時期により高度な身体を使う遊びや
スポーツ、バランス練習などを行うことで、
小脳の認知機能と情緒・社会的側面の発達が進みやすい状態を作る事ができる」
との事。
つまり、その過程で育まれるのは単に運動能力だけではない訳で、
続く青年期に学んでいく
社会的な応用力や適応力を下支えする小脳機能を
整え備える時期でもあるとすれば、
そういう経験の機会をゼロにしてしまうのは
老婆心ながら勿体無いことの様に思う。
今回のセミナーの中で
小脳のトレーニングとしてではなく
コンディショニングとしてのエクササイズを
ご紹介戴けたのも有り難かった。
所謂トレーニングでは
強度が強すぎると感じる様なケースが
あったりもしたので。
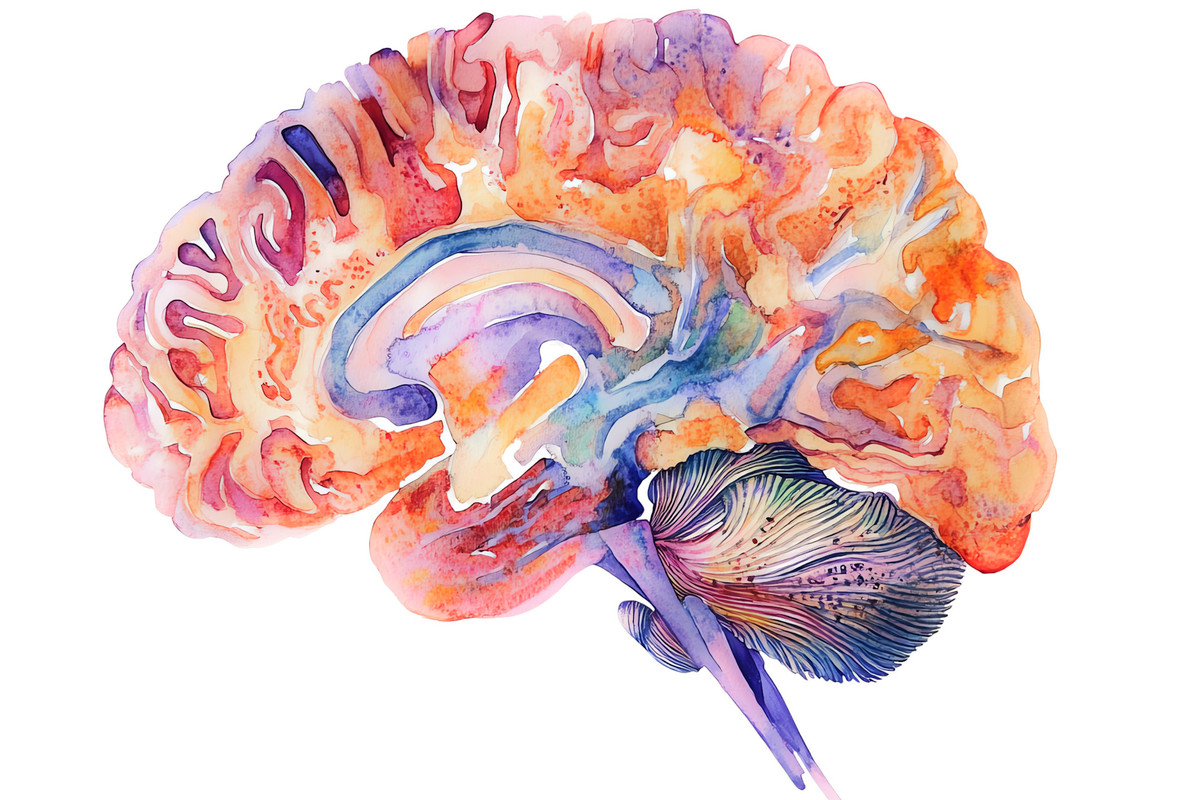
生命の不思議さに魅せられつつも
まだ学びの入り口に辿り着いたばかり。
果たして今生でどれだけのことを
学べるのかは不明だが
不思議さという柔らかい問いは
開き続けていきたいと思う。
不思議さとは、柔らかい問いのことであり、また問いを開いたままにしておくことである。つまり「自分にはわからない」、「そんなことは自分には関係がない」という、裏返された「自己正当化」を可能な限り先送りすることである。注意を向けてはいるが、特定の視点から焦点化するような問いのたて方はせず、問いそのものへとみずからを開いてしまう。それは自分自身を、世界内の疑問符にするようなものである。河本英夫『損傷したシステムはいかに創発・再生するか-オートポイエーシスの第五領域』328頁/新曜社
この記事へのコメントは終了しました。
コメント