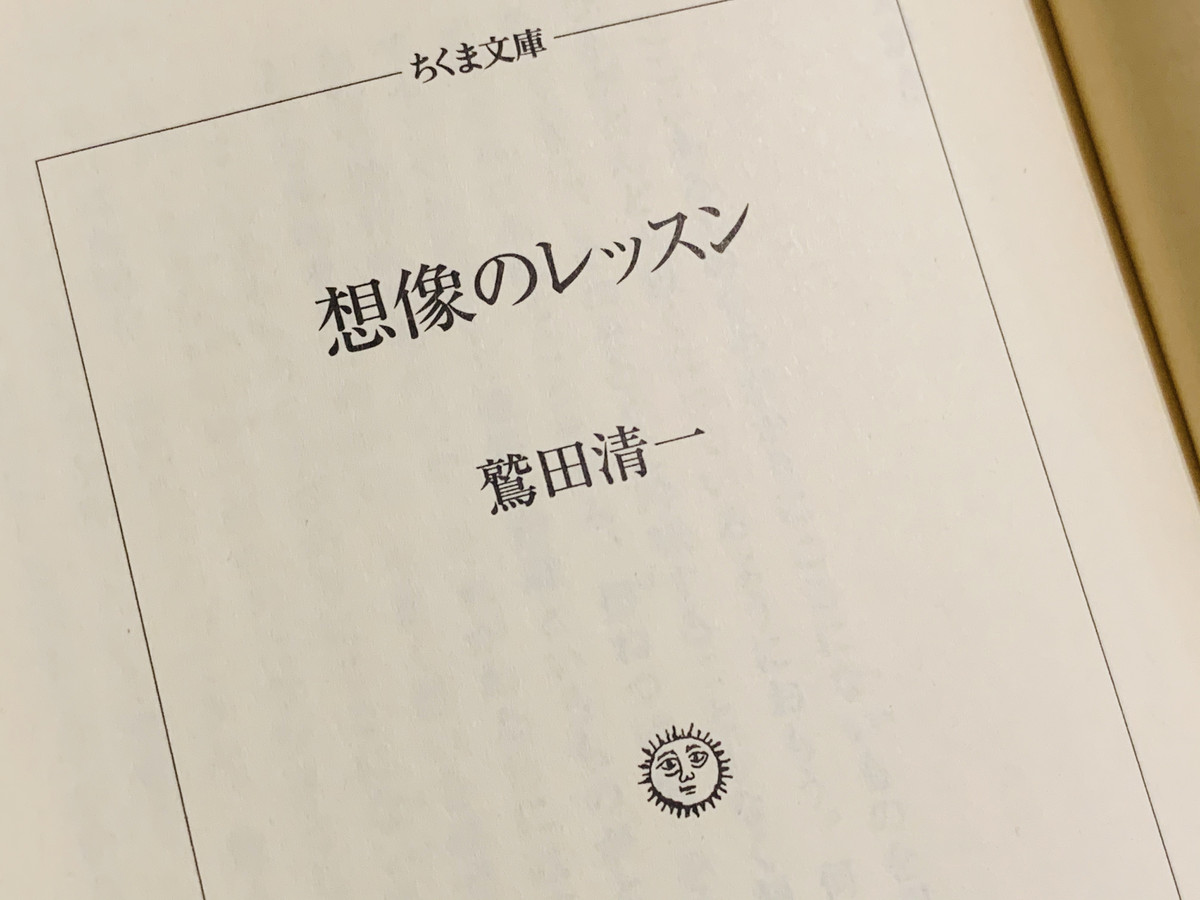
“一歩引いてかんがえる、想像する”を稽古する。
2020/04/13
若い人との会話で
SNSで流れた映像について
話題になった。
生起してくる感情や、批判する考えを
一旦脇に置いてみよう。
それがご本人のアイディアなのか
周囲の人のアイディアなのかはわからない。
でも、その発信が露わにしたものは何か。
考えてみよう。
そんな話をした。
しばらく考えて
「想像力の欠如。」
という答えがかえってくる。
想像力が無ければ
人の心を動かすことも
生命を守ることもできない。
じゃあ、今あなたは何をする?
「“一歩引いてかんがえる、想像する”を稽古する。」
彼女は言った。
少なくとも
脊髄反射的な不安や憤りとして
感情で心身をすり減らすより
自分のこととして稽えるに繋がったならば
一歩前に進めたのではないだろうか。
ならば課題図書がわりにと、一冊の本を彼女に譲った。
ここにあるものを手がかりにここにないものを想う。この力が、たとえばまだないもの、もうないものへの心のたなびきとして、希望や祈りを、想い出や咎の意識、あるいは後悔を、かたちづくってきた。他人の悲惨や困窮への思いやりを、あるいはなにがしかの義に身を捧ぐという態度を、かたちづくってきた。それだけではない。科学の仕事は、眼に見える現象を手がかりにその現象を構造的に規定している見えない規則を探究することにある。宗教的な信仰も、いまここで生きているわたしたちの世界を、その世界の外にある別の地点にまなざしの起点を置きなおして、そちらから見つめなおすいとなみだと言えるだろう。
……食がその典型だが、わたしたちは生きるためにはかならず何かを殺さなければなら、ない。たとえばそのような生存の条件をあえて見えないようにしておくシステムが、わたしたちの社会において整備されている。見たくないものを見ないで済むようにしておくシステムが、あらゆるところに張りめぐらされている。その必然の結果として、そのシステムに支払いをすれば、たいていのものは思い通りになるという感覚だけはしっかり肥大してきた。じぶんではどうしようもない条件というものが生にはあるのだから、その条件を見ないでいるというのは、あきらかに思考の停止であり、想像の失調である。
〈想像〉といういとなみは、このように、文化をその根のところで支えるものである。
支えると同時に、文化を突き動かし、それに編みなおしを迫るはずのものでもある。『想像のレッスン』鷲田清一 ちくま文庫 「まえがき」より
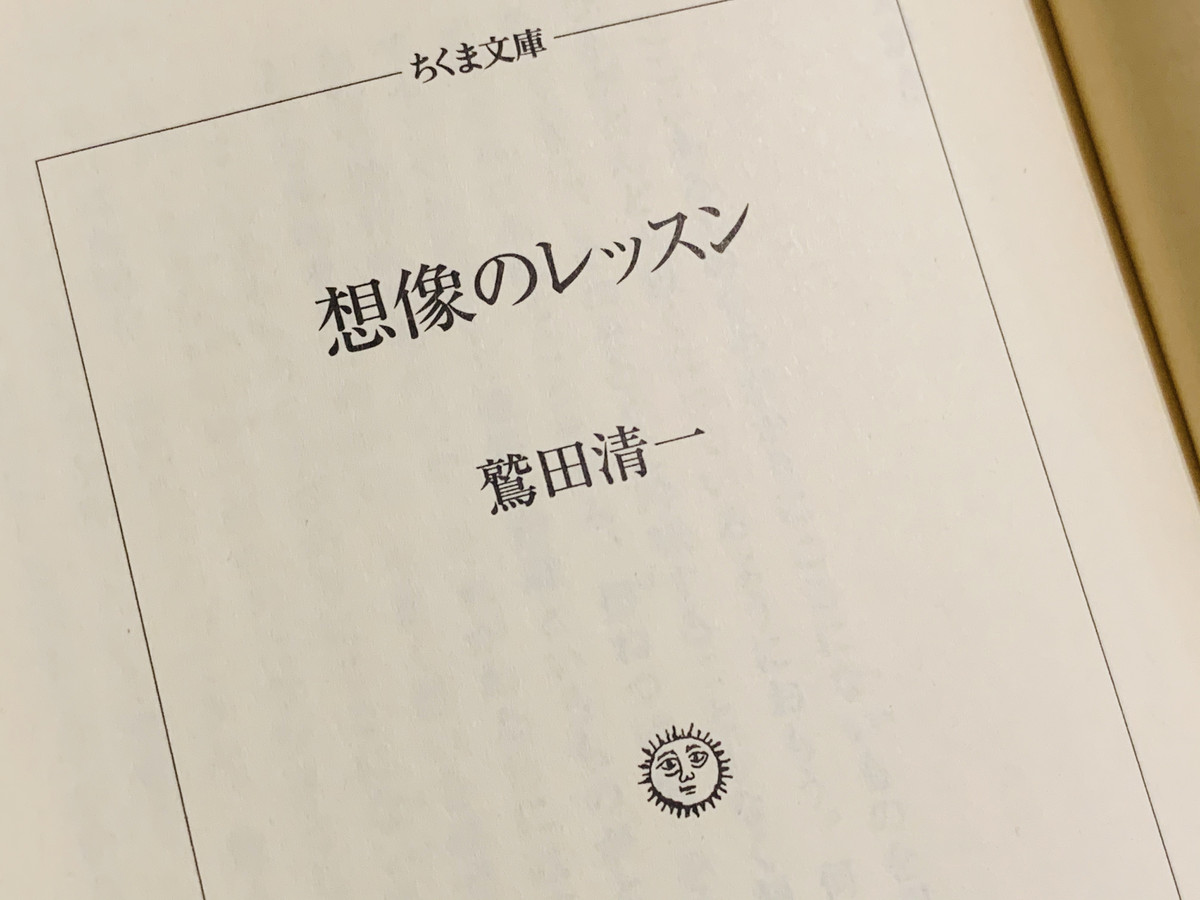
この記事へのコメントは終了しました。
コメント