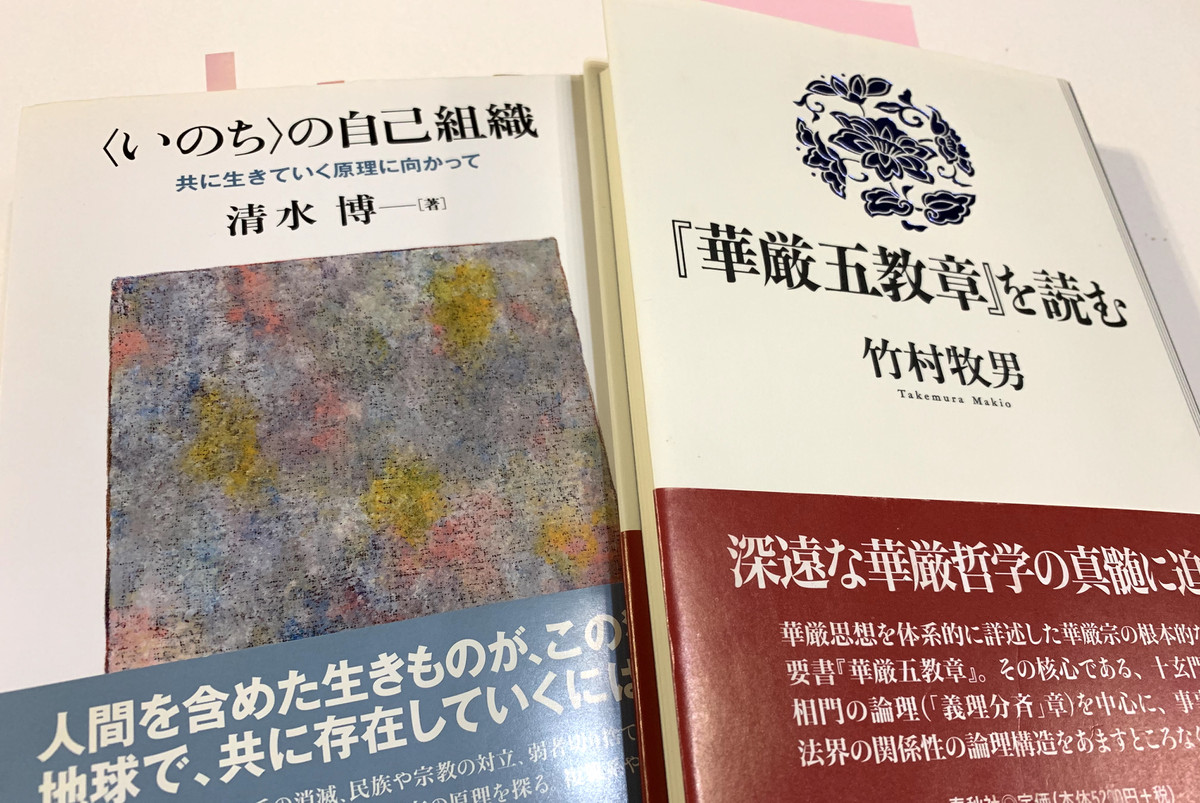
非日常的月間の徒然③
2020/04/14
『レンマ学』を読み込んでいくにあたって、もう1冊併読しているのが竹村牧男氏の「『華厳五教章』を読む」なのだが、そのページを開き始めて間もなく『<いのち>の自己組織』の清水博氏のお名前が出てきた。
私はそこで引用されていた『生命と場所ー意味を創出する関係科学』はまだ拝読していないが、今日は『<いのち>の自己組織』の付録のページから一部を引用させていただこうと思う。
ここでせっかくですから、「私は地球であり、地球は私である」という言葉と、大森曹玄が指摘した華厳の法理である「一即一切、一切即一」(『鐵舟』平成二十七年春号)の関係を振り返って見ることにしましょう。存在の世界があるときに、そこに存在している存在者全部を「一切」と呼び、任意の個々の存在者を「一」と呼びます。したがって華厳の法理は、存在の世界の「任意の存在者はすべての存在者に存在し、すべての存在者は任意の存在者に存在する」ということが、存在の理であると言っていることになります。このことを、次のように説明する人もいます。「人間の身体を構成する約六十兆個と言われる細胞は、相互に異なりながら、すべてと密接に依存しあって生きている。その状態はすべての細胞が他のすべての細胞の状態を自己の内部に包んで生きている、と言ってもよいであろう」。
たとえば、優れたサッカーのチームの各選手の運動は、競技場のグラウンドにおける他の選手全部の動きと、相互に密接に関連しておこなわれますから、「一即一切、一切即一」が生まれているということができるでしょう。それでは、どのようにして、個(一)と全部(一切)の間に、この関係が生まれるのかと考えてみると、すべての選手は自己自身を含めた「グラウンド全体」の状態を純粋経験として掴みながら、〈いのち〉の自己組織によって「〈いのち〉のシナリオ」を共有し、そのシナリオの上で変化がおきると想定して、互いの活きを最もよく引き出すように動くと思われます。ここで純粋経験とは、プレーをしている選手のように、サッカーがおこなわれているグラウンドの状態を、自分自身もそのグラウンドの一部となって、認識することを言います。それは、観客の場合のように、自分と切り離して、グラウンドを認識することとは異なっています。ここで何を言いたいかというと、グラウンド全体「一」から自己が受ける純粋経験を通して、「一即一切、一切即一」が、〈いのち〉のシナリオとして生まれる、ということです。全体(「ー」)と異なって、全部(一切)には、見かけの上で居場所は入っていませんが、実際には、居場所の〈いのち〉の活きによって、その関係が生まれているのです。また「一即一切、一切即一」は、グラウンドでは、選手誰もが主役、ということです。『<いのち>の自己組織』 清水清 東京大学出版会
生徒さんには、この例えの中の「選手」を「ダンサー」に、「グラウンド」を「舞台」に置き換えて読んでみてもらっても良いのではないかと思う。
先日の学生さんが「気持ちの悪い力」と振り返ったのは、個と全体の関係性が切り離された「閉じている」ところで生じた感触だと思う。
逆に言えば、私が「心地よいダンス」と感じるのは「一即一切、一切即一」が生まれているダンスということだ。
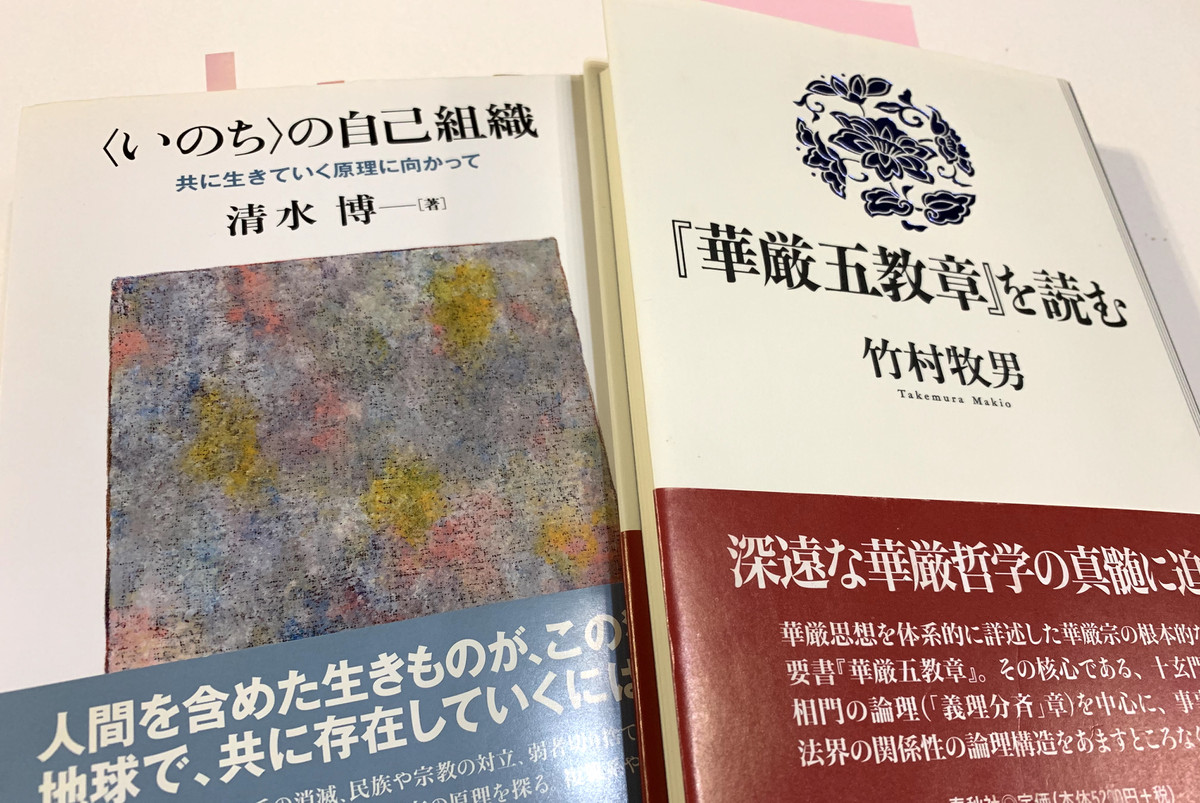
この記事へのコメントは終了しました。
コメント