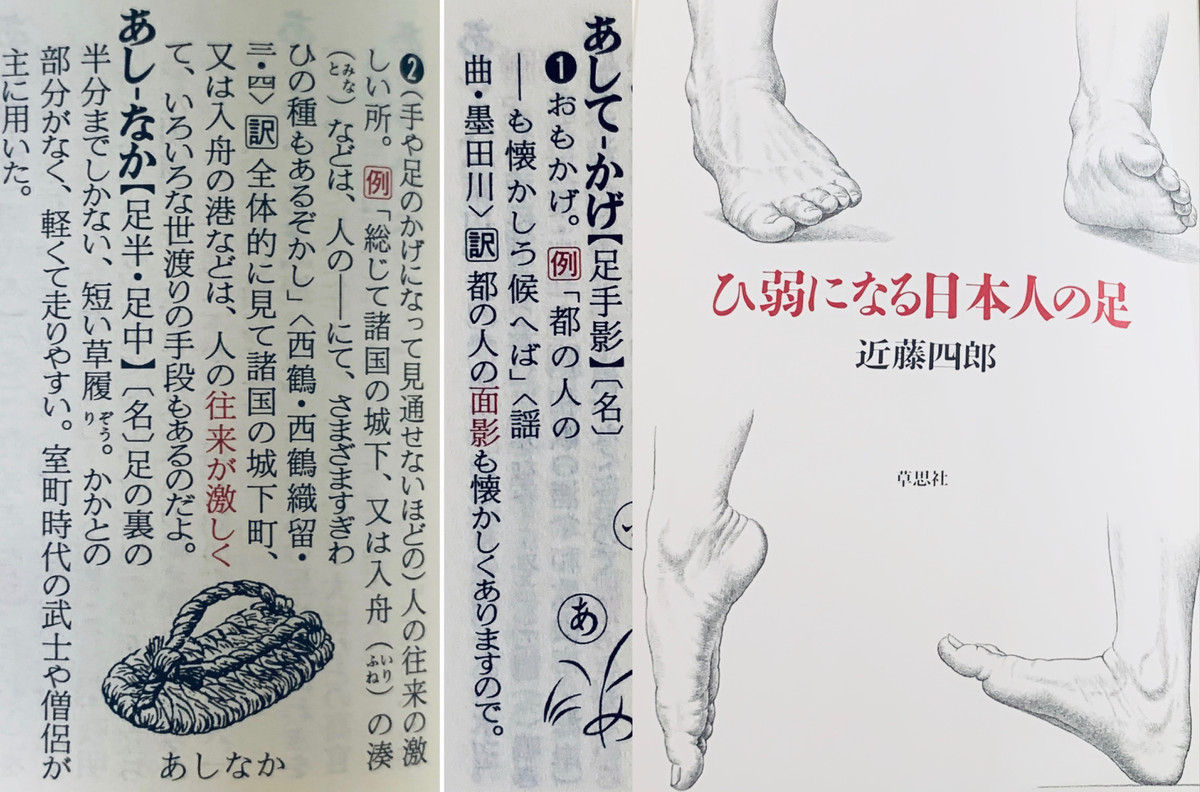
足手影
2021/06/25
古語辞典で足半を引くと
そのひとつ手前に収録されているのが
「足手影」という情緒豊かな言葉。
この言葉に初めて触れたのは
近藤四郎博士の『ひ弱になる日本人の足』を読んだ時だ。
ところで私たちは、自分に近い人のことを偲ぶとき、その人のどこを、何によって思い起こそうとしているのだろうか。どうも、その人の面影としては、まず顔が浮かんできて、次にその人の言葉が思い出されるようだ。その人の面影として、その足や手の影を思い起こそうとしても、天気快晴のもとで、広々としたところを一緒に歩き回ったりしたことがなければ、その人の足手影を偲ぶ術もない。
ことほどさように、現代の人びとの付き合いは、自分の言葉や文字も相手のそれも、大がかりな通信ネットワークの中に、いくつかの点や線として組み込まれているにすぎないということであろうか。なるほど、仕事をしているときなども、動いているのは機械だけであって、人のほうで動いている、あるいは働いているのは、手先、目、頭だけであって、体全体が動いているわけではない。
足手影が面影を表すということは、昔の人は、足と手が陽の光を受けている影というだけでなく、その影に、人の動き、身ぶり、しぐさ、ひいては人と人の出会いや付き合いに通じるものを読み取っていたということではなかろうか。それだけに、足手影から人と人の面影が身近なものとして浮び上ってくるのであろう。
近藤四郎『ひ弱になる日本人の足』草思社 177ー178頁
足手という言葉が
手足という言葉にひっくり返ってしまったのが近代だとしたら
様々な行動制限を余儀なくされたこの1年半は
それが更に加速してしまったような時間かもしれない。
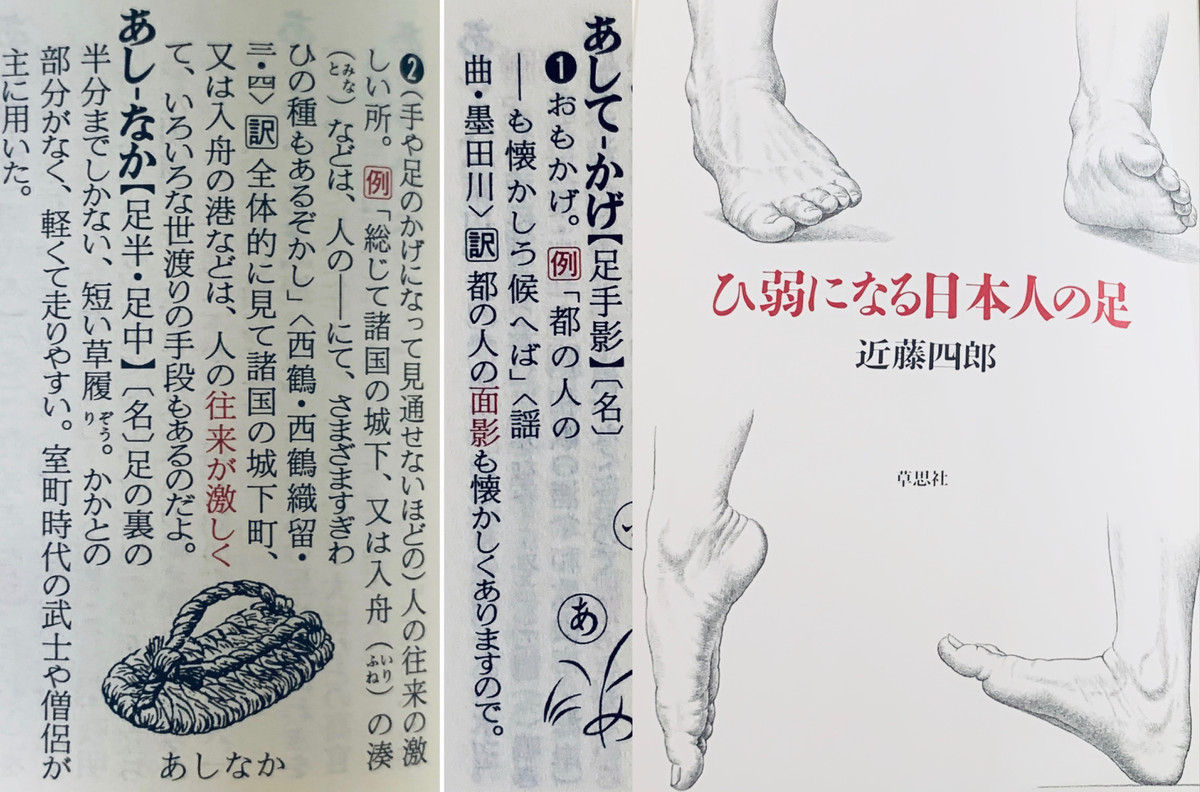
私の学びの道はずっと
踊ることや動くことに関わることだったから
自分の中に刻まれている師の記憶は
やはり面影というよりは
導かれつつ歩んだ道の足手影の像に
印象的な言葉がコラージュされているような感じだ。
そして、それは
いわゆる「稽古」の時間の中より
隅田川沿いの桜の道であったり
鞍馬山や比叡山に向かう道であったりと
水や森の感触を味わいながら
共に歩いた記憶の方が鮮やかでもあるし
その学びの本質は
その最中以上に
長く伸びた足手影のように
余韻となって響き続け
5年、10年経っても色褪せず
むしろ時を経て
自分の中でより鮮明になっていくように感じている。
この記事へのコメントは終了しました。
コメント