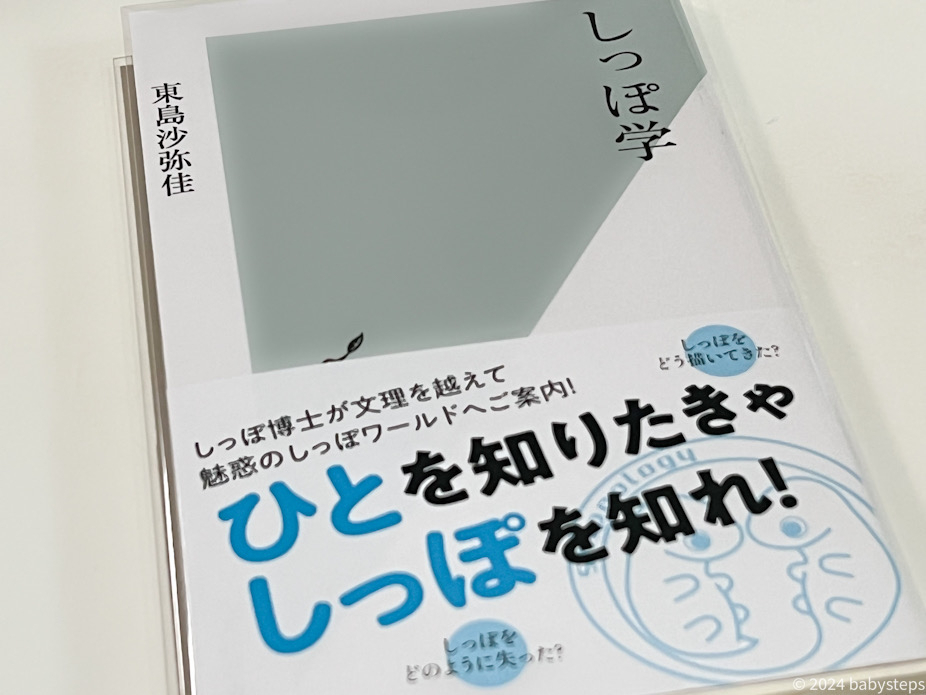
東島沙弥佳 『しっぽ学』
2024/08/26
タイトルに妙に惹かれて買った『しっぽ学』という新書。
しっぽろじー(Shippology)研究者の著者のライブ感溢れる研究にまつわるエピソードや、そもそもしっぽとは何ぞやというところから、その基礎知識が実にわかりやすく面白く綴られていて、ワクワクしながら一気に読んでしまった。
賢い人というのは例え話を用いるのが本当に上手い。
そして、アカデミックな世界あるあるの出来事へのチクリと刺さる様な言葉も、どこかからりと明るくて、読みながらニヤリとしてしまう。
著者の言う通り、今の私にとって「しっぽ」という言葉が齎すイメージは身近に居る愛犬のフサフサとした、豊かに感情を表す愛らしいものだが、時代や文化や宗教観によってはネガティブなイメージを伴うものとして捉えられたり、言語表現に用いられてきたという話や、私たちは進化の過程で一度、そして発生(胚の段階)の過程で一度、つまり二度しっぽを失くしているという話も「個体発生は系統発生を繰り返す」という三木成夫氏の著書の記憶も重なりつつとても興味深かった。
MonkeyとApeの違いや身体的特徴など、これまで曖昧にしか区別できていなかった事もこの本を読んで初めてクリアになった。
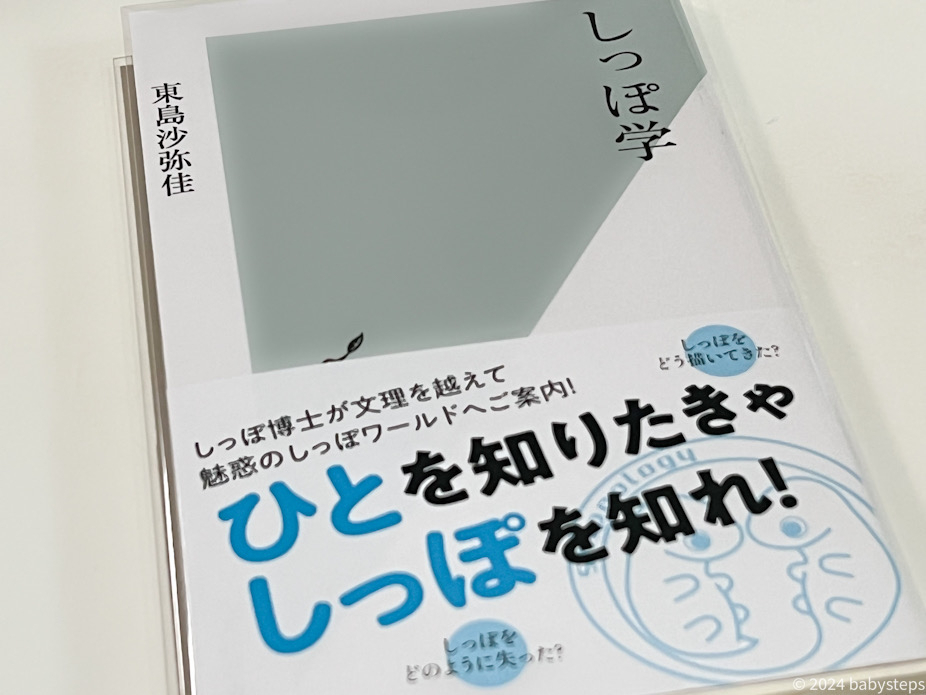
それにしても、この「しっぽ」という言葉に何故こんなに愛着を覚えるのか。
それは先にあげた愛犬たちのイメージだけでなく、その失くしたはずのしっぽのイメージを普段から活用していることもあるかもしれない。
ボディワークで尾骨をしっぽのように動かすイメージを用いることがあるが、私の場合実際に存在する尾骨にダイレクトに意識を向けると妙な力が生じてしまう気がするので、イメージの中で拡張された、猫のように自在に動く長いしっぽを想像しながら身体を動かしたり、姿勢を顧みたりする事が多い。
機能神経学のエクササイズのhourglassでも、動かしている身体それ自体ではなく、その幻のしっぽの先が床に描く円を想像する様に。
幻のしっぽで床に絵を描く、そんなワークも面白いかもしれない。

今朝もフサフサのしっぽの主と山並みを眺めに。
この記事へのコメントは終了しました。
コメント